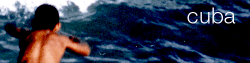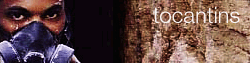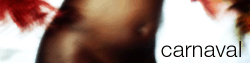|
1968擭3寧13擔嫗搒巗惗傑傟丅僲儞僼傿僋僔儑儞嶌壠丅憗堫揷戝妛朄妛晹懖嬈屻丄彫妛娰偵擖幮丅亀廡姧億僗僩亁曇廤晹側偳傪宱偰丄1999擭枛偵戅幮丅僒僢僇乕丄僴儞僪儃乕儖丄栰媴側偳僗億乕僣傪拞怱偵僲儞僼傿僋僔儑儞傪庤偑偗傞丅 挊彂偵亀cuba 儐乕僂僣側妝墍亁 (傾儈儏乕僘僽僢僋僗)丄亀崯張偱偼側偄壗張偐傊丂峀嶳朷偺挧愴亁 (尪搤幧)丄亀僕乕僐僕儍僷儞11偺僽儔僕儖棳曽掱幃亁 (島択幮僾儔僗兛暥屔)丄亀倂攖價僕僱僗30擭愴憟亁 (怴挭幮)丄亀妝揤偑嫄恖偵彑偮擔亅僗億乕僣價僕僱僗壓崕忋亅亁 (妛尋怴彂)丄亀倂攖偵孮偑傞抝偨偪乗嫄戝僒僢僇乕價僕僱僗偺埮乗亁(怴挭暥屔)丄亀曈嫬梀婰亁(奊丒壓揷徆崕丂塸帯弌斉)丅 12寧偵亀嬼慠姰慡丂彑怴懢榊揱亁(島択幮)傪忋埐丅憗堫揷戝妛島巘偲偟偰亀僗億乕僣僕儍乕僫儕僘儉榑亁傪扴摉丅憗堫揷戝妛僗億乕僣嶻嬈尋媶強 彽阗尋媶堳丅擔杮懱堢嫤夛敪峴亀SPORTS JUST亁曇廤埾堳丅憂嶌廤抍亀乮姅乯Son-God-Cool亁戙昞庢掲栶幮挿丅垽幵偼丄僇儚僒僉Z1丅twitter :@tazakikenta |
2011擭8寧17擔
偙偙偺偲偙傠丄傏偔偺杮亀儚乕儖僪僇僢僾偵孮偑傞抝偨偪亁傪撉傫偩偲偄偆恖偵懕偗偰夛偄丄懕曇傪彂偐側偄偺偐偲恞偹傜傟偨丅
傏偔偑偙偺杮傪彂偒偨偄偲巚偭偨偺偼丄屻彂偒偵彂偄偨傛偆偵丄俥俬俥俙偺傾儀儔儞僕僃傗UEFA偺儓僴儞僜儞丄揹捠偺崅嫶偝傫側偳丄枺椡揑偱埆偺擋偄傪傉傫傉傫偝偣偨抝偨偪偑偄偨偐傜偩偭偨(僽儔僕儖嵟屆丄傕偟偐偟偰悽奅嵟屆偺戙棟恖偐傕偟傟側偄僄儕傾僗丒僓僋乕偵庢嵽偟偨偺偼傏偔偩偗偩傠偆)丅巆擮側偑傜丄僒僢僇乕奅偵偦偆偄偆崄傝偺偡傞恖娫偑彮側偔側偭偨丅
椺偊偽丄峀崘戙棟揦偱僒僢僇乕偺扴摉傪偟偰偄傞偩偲偐丄姤僗億儞僒乕偱僗億乕僣價僕僱僗傪扴摉偟偰偄傞偲旲崅乆偵尵傢傟偰傕丄強慒偼僒儔儕乕儅儞偱丄偨傑偨傑偨偦偺晹彁偵攝懏偝傟偨偩偗偱偟傚偲巚偭偰偟傑偆丅
揹捠偺崅嫶偝傫偼僒儔儕乕儅儞偱偼偁偭偨偑丄椙偔傕埆偔傕挻墇偟偰偄偨丅斵偑偄側偗傟偽丄ISL偼弌棃側偐偭偨偩傠偆偟丄2002擭偺W攖傕側偐偭偨偐傕偟傟側偄丅崅嫶偝傫偵尷傜偢丄彮偟慜偺僒僢僇乕奅偵偼偦偆偟偨噣庢傝懼偊噥偺棙偐側偄恖偑戲嶳偄偨丅偩偐傜丄傏偔偼柺敀偄偲巚偭偨丅擔杮偺僒僢僇乕偼側偱偟偙偑悽奅僞僀僩儖傪妉摼偟丄塅嵅旤偺傛偆側嵥擻傪惗傒弌偟丄埨掕惉挿婜偵擖偭偰偄傞丅扤偑傗偭偰傕偦傟側傝偵偆傑偔峴偔偩傠偆丅
恖偼塭傗埮偵庝偒偮偗傜傟傞傕偺偩丅
彑怴懢榊偝傫偺昡揱傪傑偲傔傞偵偁偨偭偰丄愄偺儊儌傪尒捈偟偰傒傞偲丄彑偝傫偑柺敀偄偙偲傪尵偭偰偄傞偙偲偵婥偑偮偄偨丅
彑僾儘偵峴偔偲丄彑偝傫偼偄偮傕儚僀僪僔儑乕傗僪儔儅偺嵞曻憲傪偣傢偟側偔僠儍儞僱儖傪曄偊側偑傜尒偰偄偨丅僪儔儅傪尒側偑傜丄敄偭傌傜偄栶幰偑憹偊偨偲扱偄偰偄偨丅
乽塭傪帩偭偰偄傞恖娫偩偐傜偙偦丄岝傝婸偔傕偺偑弌偰偔傞丅塭偐傜弌偰偔傞偦偄偮撈帺偺惗偒曽丄岝偵恖偼摬傟傞傫偩乿
偙偺儊儌傪尒偨帪丄埳椙晹廏婸偝傫傪巚偄弌偟偨丅
偙偙偵傕彂偄偨傛偆偵丄傏偔偼俆寧偵斵偲夛偭偰偄傞丅
寢壥揑偵偼丄偦傟偑惗慜嵟屻偺僀儞僞價儏乕偵側偭偰偟傑偭偨丅戝戭暥屔偱専嶕偟偨帪丄斵偺僀儞僞價儏乕偼傎偲傫偳側偐偭偨丅僾儔僀儀乕僩偵傑偱摜傒崬傫偱怓乆偲榖偟偨偺偼丄嵟弶偱嵟屻偩偭偨偐傕偟傟側偄丅
亀SPA!亁偺尨峞偺拞偱丄斵偼傏偔偵乽傾儊儕僇偵峴偔傑偱帺暘偺晝恊偑傾儊儕僇恖偲偼抦傜側偐偭偨乿偲尵偭偨丅 偙傟偼杮摉偱側偄偐傕偟傟側偄丅偨偩丄朣偔側偭偨屻偵廡姧暥弔偑彂偄偨傛偆偵(偙傟傑偱壗搙傕摨偠偙偲偑彂偐傟偰偄傞偑)丄傾儊儕僇偵峴偭偨嵟戝偺棟桼偑晝恊傪扵偡偨傔偲偄偆偺偵傕庱傪傂偹偭偰偟傑偆丅 斵偑帺暘偺晝恊傪抦傝偨偄偲巚偭偰傾儊儕僇偵峴偭偨偵偟偰偼丄偦偺屻偑側偄丅埳椙晹偝傫偼丄晝恊偺偙偲偵偮偄偰扺乆偲偟偨挷巕偱榖偟偨丅乽擭偵擇夞丄抋惗擔偲僋儕僗儅僗偖傜偄偱楢棈傪擖傟傞偖傜偄偱偡丅偦傟偼儚僀僼偑傗偭偰傑偡乿偲偄偆偺偼塕偱偼側偄偩傠偆丅
斵偼栰媴慖庤偲偟偰弮悎偵嵟崅曯偺晳戜偵棫偪偨偐偭偨丅偦傟偩偗偺偙偲偩丅帺暘偺晝恊偑傾儊儕僇恖偱偁偭偨偙偲傪抦傜側偐偭偨丅斵偑偦偆巚偭偰梸偟偄偺側傜偽丄傏偔偼怣偠偨偄丅偦傟偑斵偺傛偆側嵥擻偁傞恖娫偵懳偡傞宧堄偩偲巚偭偰偄傞丅 埳椙晹廏婸偼塭傪帩偭偰偄偨丅偦偟偰丄塭偐傜岝傪敪偟偰偄偨丅偦偆偟偨恖娫偑偙偺悽偐傜偄側偔側偭偨偙偲偑惿偟偄丅敄偭傌傜偔偰丄僾儔僗僥傿僢僋偺傛偆側庤怗傝偺恖娫偑憹偊偰偄傞悽偺拞偱丄斵偵夛偊偨偙偲傪岝塰偵巚偆丅

埳椙晹偝傫傪嶣塭偟偨儀僯僗價乕僠丅懢梲偺岝傪峥偟偦偆偵庤偱幷傝丄惵偄嬻偵懳偟偰攚拞傪娵傔傞傛偆偵曕偔斵偺巔偑報徾揑偩偭偨丅