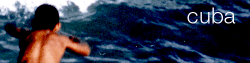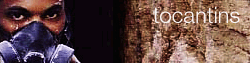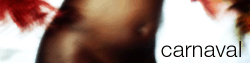|
1968年3月13日京都市生まれ。ノンフィクション作家。早稲田大学法学部卒業後、小学館に入社。『週刊ポスト』編集部などを経て、1999年末に退社。サッカー、ハンドボール、野球などスポーツを中心にノンフィクションを手がける。 著書に『cuba ユーウツな楽園』 (アミューズブックス)、『此処ではない何処かへ 広山望の挑戦』 (幻冬舎)、『ジーコジャパン11のブラジル流方程式』 (講談社プラスα文庫)、『W杯ビジネス30年戦争』 (新潮社)、『楽天が巨人に勝つ日-スポーツビジネス下克上-』 (学研新書)、『W杯に群がる男たち―巨大サッカービジネスの闇―』(新潮文庫)、『辺境遊記』(絵・下田昌克 英治出版)。 12月に『偶然完全 勝新太郎伝』(講談社)を上梓。早稲田大学講師として『スポーツジャーナリズム論』を担当。早稲田大学スポーツ産業研究所 招聘研究員。日本体育協会発行『SPORTS JUST』編集委員。創作集団『(株)Son-God-Cool』代表取締役社長。愛車は、カワサキZ1。twitter :@tazakikenta |
2011年10月28日
二十代にどんな人間と会うことができるか。これがその後の人生の全てではないにしても、大部分を決めてしまうような気がする。
振り返ってみると、ぼくの二十代は幸福だったと思う。
「週刊ポスト」で働いていた時、週刊誌が売れており、編集部の周辺は活気があった。売れているところには、才能のある人間が集まるものである。
例えば――。
ポストに配属された年の終わり、上司から「来年の注目アイドルのワイド記事をやるから、お前が面白いと思う人間のところに会いに行って来い」と言われた。ぼくが選んだのは、会社を興したばかりのテリー伊藤さんだった。
テリーさんとの付き合いは、その後も続き、注目選挙区を回って、記事を作ったこともあった。テリーさんが最初に小沢一郎さんに会ったのは、週刊ポストの誌面上だった。彼はその後、政治にも深く関わっていくようになる。
作家で言えば、戸井十月さん、猪瀬直樹さん、井田真木子さん、吉田司さん、一志治夫さん――彼らが何を考え、どんな風に取材しているのかを聞くことは、ぼくの貴重な財産になった。
当時の岡成編集長は週刊誌作りの天才とも言える人だった。賑やかで楽しく、そして厳しい雰囲気の編集部で、育ててもらったことを今でも感謝している。
そして何より、ぼくは二十代で勝新太郎さんと会うことが出来た。
12月発売の「偶然完全 勝新太郎伝」(講談社)の中にも書いているように、ぼくが勝さんと初めて出会ったのは、94年の初夏だった。
ぼくは連載班へ移り、勝さんの新連載を任されることになった。勝新太郎の人生相談である。連載開始前、ポストでコラムを持っていた内舘牧子さんと対談してもらった。
(カツシンってどんな人なんだろう)
赤坂のしゃぶしゃぶの店で、緊張しながら待っていたことを思い出す。
この続きは、また来週にでも――。

勝さんが大好きだった、京都の「河道屋」の鍋。昨年の冬、京都駅からタクシーに乗って行き先を言うと、「若いのに良く河道屋なんか知ってますなぁ」とちょっと驚いた顔をした。運転手は「勝新が好きな店でっしゃろ」と付け加えた。勝さんの本を書いているのだという話で、聖護院に着くまで話が続いた。
勝さんが、桑名正博さん、内田裕也さんたちとこの鍋を食べに行った話を、本に書いた。勝さんらしい笑える話が、京都のあちらこちらに転がっている。
2011年10月14日
大阪出張に持って行った、単行本の再校ゲラを戻した。タイトルは、「偶然完全 勝新太郎伝」になった。偶然完全とは、勝さんが良く口にしていた言葉だ。彼の芝居に対する考えを端的に現している。
原稿用紙六百枚を超える本になった。これまでで一番自信のある作品と言ってもいい。発売は12月あたま。早くみんなに読んで欲しいと思っている。

ノンフィクションの書き手は労力の割に報われることの少ない職種だと思う。この本のために、様々な場所に取材に行った。写真は、昨年夏に訪れたホテルフジタ京都から見る賀茂川。勝さんの定宿だった。ぼくが勝さんを追いかけて、京都に行ったとき、このホテルで待っていた話が本に出てくる。空気を感じたくて、ホテルに頼んで勝さんが使っていた部屋を見せて貰った。このホテルも今年あたまに閉館した。時代の流れを感じる。
2011年10月14日
大阪出張から帰京。
『フットボールサミット』(カンゼン)が書店に並んでいるようだ。今回は一冊まるごと、三浦カズさんの特集。この中で、カズさんの父親、納谷宣雄のノンフィクションと、揺籃期とも言えるブラジル時代について書いている。
カズさんは、ぼくにとって特別な選手である。97年から一年間、南米放浪をしていた時、サンパウロのある彼のアパートを借りていた。正確に言えば、納谷さんから借りていた。
その辺りのいきさつについては、「スポーツコミュニケーションズ」に連載している、国境なきフットボールで書いている。
http://www.ninomiyasports.com/sc/modules/bulletin/article.php?storyid=3204

2011年10月01日
今月から、後期の授業『実践スポーツジャーナリズム演習』が始まった。
たまに大学でどんなことを教えているのかと尋ねられる。
ぼくは「スポーツジャーナリスト」、あるいは「ジャーナリスト」などと勝手に肩書きをつけられることがある。確かに、スポーツに関する原稿は多い。ジャーナリストという言葉には様々な定義もある中、〝ジャーナリスト〟的な仕事をすることもある。
ぼく自身が名乗る時は、「ノンフィクションライター」もしくは「ノンフィクション作家」としている。
そんなぼくが、どうして〝スポーツジャーナリズム〟を教えるのか――。
自分の仕事は、人を描くことだと思っている。
昨年出した本は、絵描きの下田昌克との紀行『辺境遊記』であり、次の本は俳優の勝新太郎さんの評伝である。書きたいと思う対象に、スポーツ選手がたまたま多いだけだ。
授業で教えるのも、スポーツを通して人を描くことである。政治や経済などと比べて、スポーツはエンターテインメントの要素が強く、人を描くにはいい訓練になる。
自分が書いてみたい企画、誰に話を聞きたいのか考える。資料を集めて準備し、企画書、手紙を書いて取材を申し込む。そして、適度な敬意を持って、誠意ある取材をする。取材内容と資料を照らし合わせて、間違った情報を除いていく。残った材料をどのように組み立てれば読みやすいか考えて、原稿を執筆する。
ごく当たり前のことだ。
この当たり前のことができない〝プロ〟の記者、ライター、編集者が少なくない。ぼく自身、取材を受ける機会もあるので、寂しい思いをすることがある。
授業の中では敢えて、各スポーツの技術、戦術等には触れない。
この分野は、高いレベルでプレー(指導)をした経験のある人間が圧倒的に有利であるし、説得力がある。どちらかと言えば、経験の浅い人間の思い込みは、取材の妨げになると感じている。試合、練習を見て、スポーツの取材を続けていれば、否が応でも競技の知識は頭に入ってくる。誰に聞けば正しい知識を手に入れることが出来るかという嗅覚を身につける方が大切だと思う。
ぼくの授業では、誰をどのように取材するのか、どんな原稿を書くのか、一切指示しない。取材機会を与えて原稿を書かせても、誰が書いても変わらない面白みのないものにしかならない(記者クラブの人間の書く、原稿のつまらなさを見れば分かる)。
自分で書きたいと思う人間を探して、アポイントメントをとることから始める。一問一答、ニュージャーナリズム的手法等、執筆の基本は教えるものの、集めた素材をどの形で原稿に仕上げるのかは任せる。
約四ヶ月掛けて、手紙、企画書、交渉の経緯を報告しつつ、出来上がった作品を皆で話し合って、完成度を上げていく――。
人間は自由にやっていい、と言われると考えるようになるものだ。自分で考え、手に入れたものでなければ、結局身につかない。
きちんと人に応対して、取材して話を聞くことは、スポーツジャーナリズムに限らず、全てのジャーナリズムの基本である。正しい情報収集という意味で言うならば、どんな職種にも必要な、最低限の技術かもしれない。
良く言われるように、人に教えることは、教えられることでもある。学生と話しながら、真っ当に取材する必要性を改めて噛みしめている。