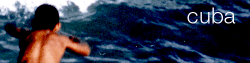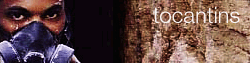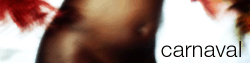|
1968年3月13日京都市生まれ。ノンフィクション作家。早稲田大学法学部卒業後、小学館に入社。『週刊ポスト』編集部などを経て、1999年末に退社。 |
2012年10月31日
大阪の阿倍野区で行われた、桑名さんの葬儀に向かう新幹線の中で、つらつらと桑名さんとの思い出が浮かんできた。
桑名さんとは、せいぜい一年に数度、時に数年に一度程度しか会わない時もあった。ただ会う度に濃い印象がある人だった。
ぼくが初めて桑名正博という男の存在を知ったのは、小学生の時だった。彼はすでにソロデビューしており、『セクシャル・バイオレット・ナンバーワン』で人気だった。ただ、ぼくが好きだったのは、『哀愁トゥナイト』だった。『夜のヒットスタジオ』に出演した桑名さんは、格好良かった。格好いいけど、この人と一緒にいると〝ヤバい〟とは子ども心なりに感じた。その時の映像をYouTubeで見つけたと、ずいぶん仲良くなってから桑名さんに話したことがある。
「あー、夜ヒットの奴やろ。たぶん、あの何日か後にパクられたんや」
と桑名さんは笑った。子供の勘は当たっていた訳である。
先日の『日刊ゲンダイ』の記事では、2009年のニューイヤーロックフェスin上海の収録に同行した話を書いた。
☆ ☆ ☆ ☆
覚悟はしていたので、訃報を聞いた時はとうとうその時が来たのかと思った。しばらくしてから、ずっしりと重い哀しさが追いかけてきた――。
二十六日、ミュージシャンの桑名正博さんが亡くなった。大阪市内の自宅で脳幹出血で倒れてから104日目のことだった。
桑名さんと初めて会ったのは、今から十数年前になる。知人の紹介で一緒に食事をした際、共通の知り合いである故・勝新太郎さんの話で盛り上がった。音感のいい桑名さんは、勝さんの物真似が巧みだった。しゃがれた声で歌う『Sunny』は目を瞑ると、勝さんがそこにいるかのようだった。
拙著『偶然完全 勝新太郎伝』を書く時、最初に相談したのも桑名さんだった。軽井沢の桑名さんの自宅を訪ねて、話を聞いた。話は尽きず、場所を駅前の寿司屋に変えても終わらなかった。ぼくは東京行きの最終の新幹線を逃し、桑名さんの自宅に泊めて貰うことになった。
二〇〇九年の年末、上海で行われた『ニューイヤーロックフェス』の収録に同行したこともある。ライブ前日、地元の関係者からの接待でカラオケのある店へ一緒に行った。店の人間は桑名さんの来店を喜び、彼の曲を次々とカラオケに入れた。だいたいプロのミュージシャンは自分の歌をカラオケで歌いたがらないものだ。以前にも桑名さんが断ったのを見たことがあった。ましてや、ライブを控えている。歌うはずもなかった。
桑名さんの曲のイントロが流れた。ここで曲を切ってくれというと険がある。とっさにぼくはマイクをとった。『セクシャル・バイオレット』『哀愁トゥナイト』までは問題なかったが、『サード・レディー』はうろ覚えだった。すると、横に座っていた桑名さんは、「お前、よう知ってんな」と笑いながら、耳元でメロディを教えてくれた。
ライブの当日の打ち上げで、ぼくは桑名さんと深酒をして、その日泊めてもらうはずだった上海在住の友人とはぐれてしまった。桑名さんは「うちのホテルに来ればええよ」と部屋をとってくれた。翌朝、目が覚めると桑名さんは帰国の途についており、ぼくの支払いは全て済んでいた。
この埋め合わせはどこかで――という約束は果たせないままだった。勝新太郎さんと同じように、綺麗に遊ぶことができる大人がまた一人、この世から去ってしまった。
『日刊ゲンダイ』10.29号
☆ ☆ ☆ ☆
同じような話は沢山あった。ある少女漫画家たちを含めて飲みに行った時のことだ。人気漫画家だった彼女は、普段から編集者など周囲が、自分の意のままに動くと思っていた。その癖のまま、桑名さんに『月のあかり』を謳ってくれと、カラオケにいれた。この時も、ぼくは代わりに歌った。あの素晴らしい歌を本人の目の前で歌う恥ずかしさ――。それも今となってはいい思い出である。
話は尽きない――。
彼の46歳の誕生日ライブは、大阪まで見に行った。46歳になったことを「しじゅう、ロックやで」と駄洒落にしていた。ぼくももうすぐ、その「しじゅう、ロック」の年齢になる。時間の流れるのは早いものだ。
葬式では、ギタリストの原田喧太君が、弔辞を読んだ。「マサやん」と呼びかけ、最後にメンバー紹介をしたいと言った。
桑名さんのライブでは、他のメンバーはボーカルの桑名さんが名前を呼んでいく。本人だけは、自分が名乗る訳にはいかないので、原田君が桑名さんを紹介していた。
「ギター、ボーカル、桑名正博」
この本当に最後となるメンバー紹介を聞いて、思わず涙がこぼれそうになった。
その後、美勇士君を中心に「月のあかり」を演奏した。キーボードの小島良喜さんが本当に楽しそうな顔で演奏していたのが印象的だった。喪主である美勇士君は、締めくくりの挨拶で、いきなりマイクに頭をぶつけて笑いをとった。湿っぽいことの嫌いな桑名さんに相応しい、明るいお葬式だった。

祭壇には遺影と共に大量の花が飾られていた。

この後、大阪市役所を起点としてパレードを行った。
2012年10月29日
ここのところ、〆切り、取材、打合せ、取材申し込みの手紙等、仕事に追われていた。
そんな中、先週には二冊続けて原稿を書いた雑誌が発売になった。『GQ JAPAN』では中田宏さんと維新の会、『フットボールサミット』では元日本代表の廣山望君について書いている。
維新の会は、まさに今動いている最中である。何を書くべきか、最後の最後まで悩んだ。第一回目の公開討論会を中心に、中田宏さんに加えて、山田宏さんに焦点を当てることにした。
山田さんは橋下市長についてこう語っている。
「彼の強烈なエトスというのは、日本に談合体質に対する反感だと思う。(中略)彼は今まで自分を抑えつけてきたこうした談合体質に非常な嫌悪感がある。不明朗でおかしな社会を建て直さないと、自分と同じように苦労する人間が出てくる。チャンスが多くて、公平で透明度の高い社会を作ろうとしている」
彼の言動、特異なキャラクターには賛否あれど、彼の思いは本物だとぼくは思っている。
もっとも人は変節するものだ。国政政党となって、これまでとは違った動きが必要になってくる。行動が広がり、多くの人が関わることで〝純度〟が下がることもあるだろう。これからはさらに注意深く追って行きたい。
廣山君の原稿は、彼がプレーしたパラグアイ、ポルトガル、フランス、そしてアメリカの違いについて書いている。
国外で生活することは、異文化を受け容れることである。自分と違った考えを受け容れることで、人は成長する。
彼には十数年に渡って、のべ数十時間話を聞いてきた。今回、原稿を書くために、過去のインタビューデータ、取材メモを全てプリントアウトしてみた。彼を追いかけることで、ぼくも走りながら、色んなことを感じ、考えてきた。この経験が自分を物書きとして生きていく糧となっている。ぼくの人生にとっても貴重な時間だった。彼のような人間に、伴走できたことは本当に感謝している。
引退を決めた後、世界各国でプレーしたことについて、こんな風に話してくれた。
「人生で楽しいことがあることをどこの国でも教えて貰った。日本にいた時、自分が感じていた幸せは個人的で小さなものだったということが分かりました」
彼らしい言葉である。
忙しさが一段落した先週金曜日、桑名さんが亡くなったという連絡をもらった。倒れてから100日以上経っていたので、とうとうその時が来たのかという、寂しさを感じた。桑名さんは歌い手としてもギターリストとしても才能がある人だった。特に、歌のバックで弾くギターは抜群だった。ボーカリストとして、歌を生かすにはどんなギターのフレーズを弾けばいいのか、良く分かっていた。
本当に惜しい人を亡くした。今日発売の『日刊ゲンダイ』で追悼の原稿を書いている。桑名さんとは思い出が沢山あり過ぎる。散々悩んで、過去の『週刊田崎』でも書いた、2009年の『ニューイヤーロックフェス』収録に同行した時の話を原稿にまとめた。

2012年10月08日
しばらく入稿、校了、取材、打合せが立て込んでいた。Facebookには書き込んでいたものの、webの更新ができなかった。ここ数週間をざっと振り返ると――。
先月半ば、ドゥンガが急遽来日することになった。帰国の日に成田までの車に同乗して話を聞くことになった。このインタビューは翌週17日発売の『日刊ゲンダイ』から五回の短期集中連載として掲載された。ドゥンガにしては珍しいことだが、特定の選手――本田圭佑をべた褒めした。彼の気持ちの強さを本当に買っていた。ぼくも同じ意見である。
9月23日は、リングスに出場した大山峻護さんを応援するために、後楽園ホールを訪れた。
安田忠夫さんの引退興行以来、約一年半ぶりの後楽園ホールだった。
興行を主宰し、チケット売りに走り回っていた頃は、(全然売れていない…)と座席表を開く度にうんざりとしたものだ。何冊もの本を書いているので、お金を払って物を買ってもらうことの難しさを分かっていたつもりだった。しかし、チケットを売ることの難しさはまた違っていた。あの時は千人強収容の後楽園ホールが大きく感じたのに、観客として行くと狭い、と思ってしまった。人の感覚とはいい加減なものだ。
そして、9月29日からは早稲田大学で教えている後期の授業、『実践スポーツジャーナリズム演習』が始まった。
毎年、授業が始まる頃になると、自分が学生に何を教えられるのだろうと考えてきた。
出版社で働いた経験から、日本の現場では新入社員にジャーナリズムへの専門的な知識を求めていないことは分かっている。
企業がこれまでの大学教育に信を置いていないということもあるだろう。そして、日本企業の、社員を自分たちの色に染めたがるという性質もある。大学院等で学んだジャーナリズムの知識は、企業のヒエラルキーの中で邪魔になるとも考えられている節もある。
その上で、ぼくは何を伝えられるのか、何を伝えなければならないのか――。
原稿執筆の手法よりも大切にしているのは、礼儀である。
授業では取材申請の手紙の書き方から始める。そして、取材前にきちんと下調べをすることを徹底させている。国会図書館、大宅文庫の利用、本を書いている人ならば、きちんと読んでから会いに行くこと。
大したことじゃない、と思うかもしれない。しかし、こんな当たり前のことさえできない、大手メディアの人間は多い。もちろん、取材というのは対「人」なので、相性や巡り合わせがあり、必ず上手く行く方法はない。それでも人に会う前の準備を癖にしておけば、失敗は少なく抑えられる。文体を教えるよりも、ずっと大切だし、何より社会に出てから役に立つだろう。
そして、もう一つはクリエイター=作家としての背中を見せること。
例えば、後楽園ホールの安田忠夫さんの引退興行は学生にも手伝って貰った。ぼくは必死だったし、教える余裕も意識はなかった。しかし、ゼロからイベントを立ち上げること、そして面白いことをやろうという意図は伝わっただろう(興行のアウトプットは上手くいかなかったが……)。
今の若い者は……という紋切り型の言葉を聞くといつもうんざりする。若い者を嘆くあなたは、それだけ面白い生き方をしているのかと問いたくなる。
いいなという生き方をしている先輩は何人もいる。ぼくも年下から面白い生き方をしているなと思われたい。そうでないと、ぼくが教える意味がなくなってしまう。

成田空港のロビーで一枚。いい表情をしてくれた。ドゥンガとは六年ぶりの再会だった。インタビューはポルトガル語訛りのスペイン語。アルゼンチン国境に近い、ブラジル南部出身のドゥンガはスペイン語も話せるのだ。しかし、全然使っていなかったので、スペイン語もポルトガル語も全然口から出てこない! 言っていることは分かるんだけれど……。ポルトガル語のリズムを多少でも取り戻した頃には、彼の飛行機の搭乗時間になっていた。