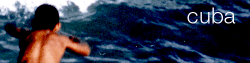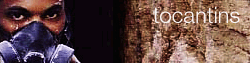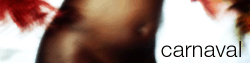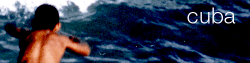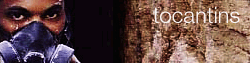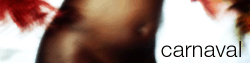|
世界各国様々な国に出かけ、スペイン語やポルトガル語などを話すので、昔から外国
語に興味があり、得意であったと思われがちである。
確かに、英語は不得意な教科ではなかった。ただ、同じ高校に通っていた鏡リュウジ
のように、ずば抜けて英語ができたわけではない。普通に受験のための英語を勉強し
ていただけだ。どちらかというと、熱心とはいえない生徒だった。
そもそも初めて外国に出たのも遅かった。
大学では国際法のゼミに入っていた。国際と着く法律を学ぼうとする生徒には、外国
人留学生、帰国子女、留学経験者が多かった。大学三年生の段階で外国に行ったこと
がないという生徒は僕を含めてほんのわずかしかいなかった。
大学三年生の終わり、春休みを使って初めての海外旅行に出かけた。
僕にとっての最初の外国は、バンコクだった。バンコク、バングラデッシュのダッカ
を経由して、カルカッタへ。ビーマン・エアラインのこの路線がインドに行くのには
一番安かったのだ。
初めての国外旅行の目的地としてインドを選んだ理由は特にない。強いて言うならば
、ブライアン・ジョーンズが、『ペイント・イット・ブラック』でインドの楽器シタ
ールを弾いている写真が頭に残っていたからだろうか。インドでシタールを習うつも
りだったので、吉祥寺でシタール演奏の基本だけは学んでいた。
バラナシーというガンジス川のほとりの街で、ラビシャンカールの弟子の弟子という
男にシタールを習うことになった。楽器屋の上に住まわせてもらい、一日八時間レッ
スンを受けていた。それ以外の時間はガンジス川をぼんやりと眺めていた。そして、
もつと世界を見てみたいと思うようになった。
インドから帰国すると、大学を四年間で出られないことが判った。一年生と二年生の
科目選択の抽選番号が極めて悪く、いわゆる楽勝科目をほとんどとることができなか
ったのりだ。留年が決まった瞬間から、僕は猛烈にアルバイトを始め、お金を貯めた
。塾の講師、家庭教師、レンタカーの配送、バーと四つ掛け持ちをしていたこともある。
四年生の夏には友人と二人で、アメリカ大陸に渡った。イージーライダーのようにオ
ートバイでアメリカ大陸を旅するつもりだった。
当時、カリフォルニア州ではヘルメットをかぶらなくてよかった。あまりに気持ちが
良かったので二人乗りしていた時、後ろに乗っていた友人がシートの上に立ち上がり
両手を広げた。
すぐにサイレンが鳴ってパトカーに止められた。警官は「ここは公道だ。サーカスみたいなことをしないように」と注意したが、見逃してくれた。
二百キロを出して、海岸沿いのハイウェイを走った。ノーヘルでそんなにスピードを
出すと、あまり気持ちが良くないことを知った。
チェーン店で大食いに挑戦したことがあった。店員が、挑発的な目をしていたので、とにかく食べまくった。多くのメニューを全部食べられるというものだったが、ほとんど食べ尽くした。しかし、あまりに脂っこくて後で吐いた。アメリカ人は太るはず
だと思った。
テキサスでは全く僕の話す英語がほとんど通じなかった。カワサキの古いオートバイ
、マッハを使って、ドラッグレースをしている面白い奴と会った。僕の乗っていたカワサキのZ1Rは、マフラーを外して直管にしていた。派手な音をまき散らせていたせいか、地元の不良たちの乗るコルベットにつけ回されたこともあった。
友人のオートバイのエンジンが壊れた時、あるオートバイショップの人間は、ジェッ
トスキーのエンジン用のピストンを削って入れた。
フロリダではオートバイ屋で修理を頼むと後回しにされ、結局断られた。明らかに人種差別されていた。日本のパスポートを見せても、見たことがないと言ってビールを
売ってもらえないこともあった。頭に来たので、オートバイのエンジンを掛けて、店の前で何度もアクセルをふかした。
そんな僕たちを見かねて、長距離トラックの男たちがビールを分けてくれた。男は「
俺もオートバイが好きだ。今もトラックの後ろにハーレーを積んでいるのだ」と目配せした。
オートバイに乗っていると、多くの場所でアウトロー扱いされる。また、ハーレーダ
ビッドソンに乗るのは白人で、黒人達はカワサキのオートバイを好むことを知った。
分の知らない面白い世界が沢山あることが、はっきりと分かった。
人間は働かなければ、食べていけない。僕は大学を五年間かかって卒業し、出版社に
就職した。バブル景気の最後で、まだ採用人数が多かった時に滑り込むことができた。
スペイン語を勉強しはじめたのは、入社して二、三年経ったころだ。
NHKのラジオ講座を録音して繰り返し聞いた。ポルトガル語は、ブラジルに滞在し
ている間に覚えた。すべて使えるようになったのは旅の中である。
言葉が使えるからこその、トラブルも起こる。
今回、ハバナのあるバーの男たちと仲良くなった。その店に行き、モヒートを頼むと
、酔っぱらいの男に下田が絡まれた。しつこいので僕が「出て行け」と言うと、男が何かを言い返した。
それを聞いて、黒人のバーテンダーは突如怒り、バーを飛び越えてようとした。もう一人のバーテンは、刃渡り三十センチ以上あるナイフを、手に持って身構えていた。
酔っぱらいは大きく手を挙げて、飛びかかろうとしたが周りの男たちに止められて引
き上げていった。仲間の襲撃を恐れたのか、バーテンたちは一気にシャッターを下ろ
した。いきなりの店じまいである。僕の言葉が引き金になって大騒ぎになってしまっ
た。
机の前で座って、おとなしく勉強するのは僕の性に合わない。転げ回り、擦り傷や痣
を作りながら言葉、人生を学んできた。そして、これからも転がっていくのだろう。
二十歳まで国外に出たことのなかった僕が、今も世界中を彷徨っている。不思議なも
のだと、ふと思うのだ。
明日の飛行機でパリを出て、日本へ向かう。久しぶりの日本である。
|