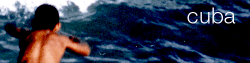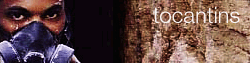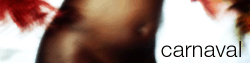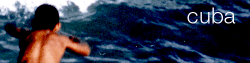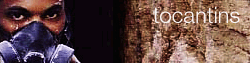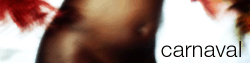来月二日から六日まで、愛知県豊田市で、ハンドボールの北京五輪予選が行われる。数年前から、僕の九月前半のスケジュールは空けてあった。以前は九月を楽しみにしていた。ただ今、その気持ちが変化している−−。
僕がハンドボールに興味を持ったのは、ここで何度も書いたが、田場裕也という選手を知ってからである。
今から約四年前の03年11月、僕は、広山望選手のことを書いた単行本『此処ではない何処かへ』が発売になった後、再び彼のいるモンペリエに向かった。
広山選手から近くのニームという街に日本人のハンドボール選手がいることを聞いた。僕は、欧州にハンドボールのプロリーグが存在すること、そこに日本人のハンドボール選手がいたことを知らなかった。
ニームに着いてみると、ハンドボール専用の体育館があることに驚いた。フランスの地方都市は街ごとに、人気スポーツが異なっている。例えば、広山選手のプレーしていたモンペリエは、当時一部リーグだったサッカーとラグビーの人気が高かった。ニームにもサッカークラブはあるが、三部リーグのため、一部リーグに所属しているハンドボールの人気がサッカーを凌いでいた。
数千人収容の専用体育館は満員だった。その中で田場裕也は中心選手として、フランス人から信頼を受けていた。僕は、彼のような日本人がいたことを知らなかった不勉強を恥じた。
試合後、ワインを飲みながらハンドボールの話を聞いた。
ハンドボールの日本代表はソウル五輪以来、オリンピックの出場権を得られていない。マイナー競技にとってオリンピックの占めている位置は大きい。しかし、アテネ五輪の予選で日本は出場権を逃していた。次の五輪、北京は絶対に行かなければならない。自分は日本代表を引っ張る力になりたいと田場は語った。その夜、僕たちは田場家にあったワインをすべて飲み尽くした。
そして、僕は彼の熱に感化されて、ハンドボールの記事を書くようになった。
ところが−−。
昨年夏、田場は故郷の沖縄に戻って、自らFC琉球ハンドボールというチームを立ち上げた。特定の企業に頼らず、プロフェッショナルな選手を集める、欧州と同様のクラブチームを目標にしていた。
僕は田場からクラブ設立について聞かされた時、猛烈に反対した。
クラブ設立のためには、欧州でプレーする機会を捨てなければならない。欧州どころか、零からクラブを立ち上げることは、県リーグから始めることになり、何年かは日本のトップの水準でさえも田場はプレーできない。
世界を知る彼は日本代表の中で貴重な存在である。欧州の厳しい環境でプレーしながら、その経験を日本代表の選手に伝え、五輪の出場を決めてから、クラブを立ち上げても遅くない。少なくとも九月の五輪予選までは、選手としてプレーすることを優先すべきだと、僕は話したが、田場は「今、やるべきだと思うんです」と譲らなかった。
昨年から今年に掛けて、沖縄に何度か足を運び、僕は少し考えを改めた。
ここ数年、大崎電気を中心とした日本リーグ、チュニジアの世界選手権、タイでの世界選手権予選に僕は足を運んでいる。
どうしてソウル五輪以来、日本代表はオリンピックに出場できなかったのだろうか、と僕は考え続けてきた。問題は、買収された審判による、不可解な笛だけでない。
継続的な成果には必ず原因がある。それまで克服できなかった壁を乗り越える時には、それなりの理由がある。
サッカーの日本代表が97年に悲願のW杯出場を決めたのは、Jリーグというプロリーグが発足したこと、それに伴って各クラブチームの下部組織が充実した。トレセンなどの中央の育成システムも機能するようになった。なにより、産業として成功したことで、ピッチ内外でサッカー界に優秀な人材が集まるようになった。だからこそ、アジア全体のレベルが上がる中で、継続してW杯出場権を獲得できている。
それに対して、日本のハンドボール界は局地的に改善している点はあるにしても、全体の流れとしていい方向に向かっているようには思えない。
間違いなく、ハンドボール日本リーグのレベルは、低下している。
韓国人のペクを除けば、かつてホンダにいたフランス人選手のようなワールドクラスの外国人選手は日本リーグにいない。 今年終了した日本リーグでは、大同の富田恭介がベストディフェンダーに選ばれた。富田は才能のある選手で、リーグで最も優れた選手の一人であることは間違いない。ただ、大学を卒業したばかりの選手がそうした賞を獲得できてしまうというのはリーグのレベルが低いことの証左といえる(富田は、今後の目標設定に困ってしまうだろう)。
今の日本リーグは企業の好意に甘えて存在している。他の競技と比べ、メディアへの露出も少なく、リーグの運営は完全な赤字体質のハンドボール競技に見切りをつければ、チームはあっけなく消滅してしまう。すべて企業頼みで、地域との緊密な連携がないため、横浜フリューゲルスが消滅した時のような抗議行動はまず起こらないだろう(もちろんこれは今、ハンドボールに関わっている人間たちだけの責任ではなく、過去の怠惰のツケであるのだが)。
田場がハンドボールの盛んな沖縄にクラブチームを作ったのは、そうした状況を変えようとしたからだ。
資金、選手集めに奔走する田場の姿を目の当たりにして、この無防備で一途な情熱だけが、静かに、そして確実に自然死へと向かっているハンドボール界に風穴を開けることができるかもしれないとも思うようになった。
現在、五輪予選の準備のため、日本代表は国外遠征に出ている。当然のことながら、田場はメンバーに選出されなかった。
田場(あるいは、東俊介選手)がいなくとも、僕は日本代表に対する思い入れがある。北京五輪へ出て欲しいと切に思っている。ただ、冷静にそれが難しいと感じている自分がいるのも事実である。
僕が今の日本のハンドボール界に対して感じている苛立ちと不安を、選手たちは肌で、より切実に感じていることだろう。日本代表に選ばれた選手たちが、ハンドボールという競技の存続を掛けて戦ってくれることが唯一の望みである。
今の日本代表選手たちからは、狂気に近い情熱を持つ田場と比べると、控えめで冷ややかな印象を受ける。それでも彼らは、田場がクラブチームを立ち上げるに至った危機感を奥底で共有していると僕は思っている。
継続的な成果と違って、突発的な奇跡は、スポーツではありうる。
日本代表選手たちの思いが瞬間的な力となり、豊田市で僕の悪い予感を吹き飛ばしてくれることを祈っている。
|